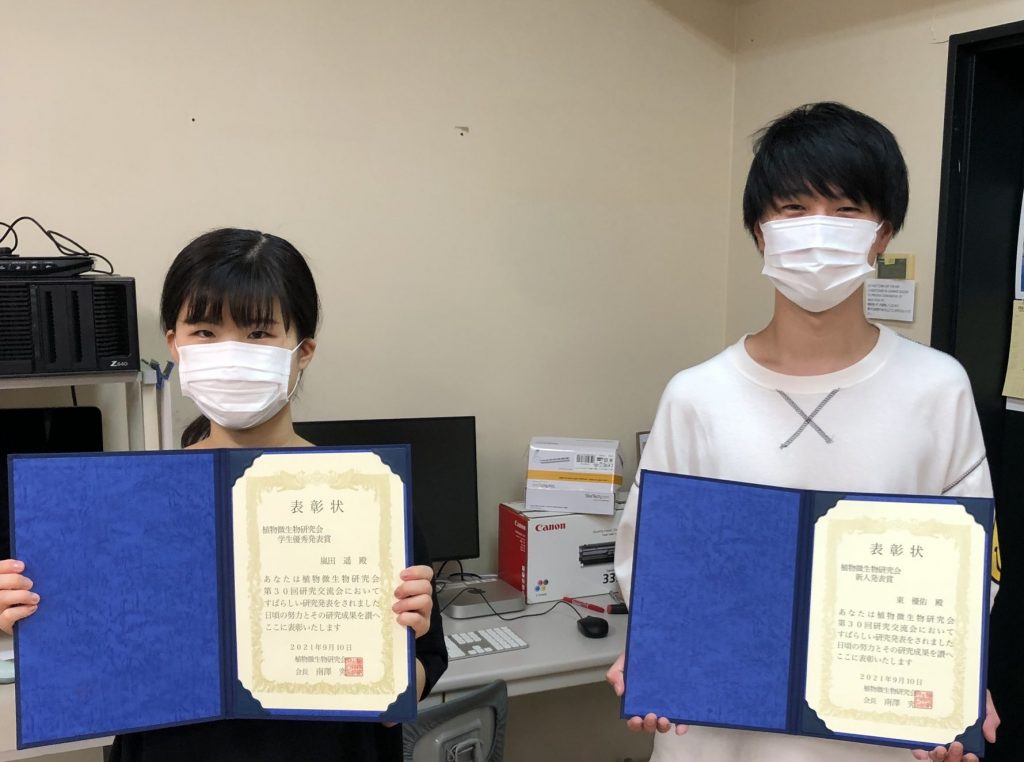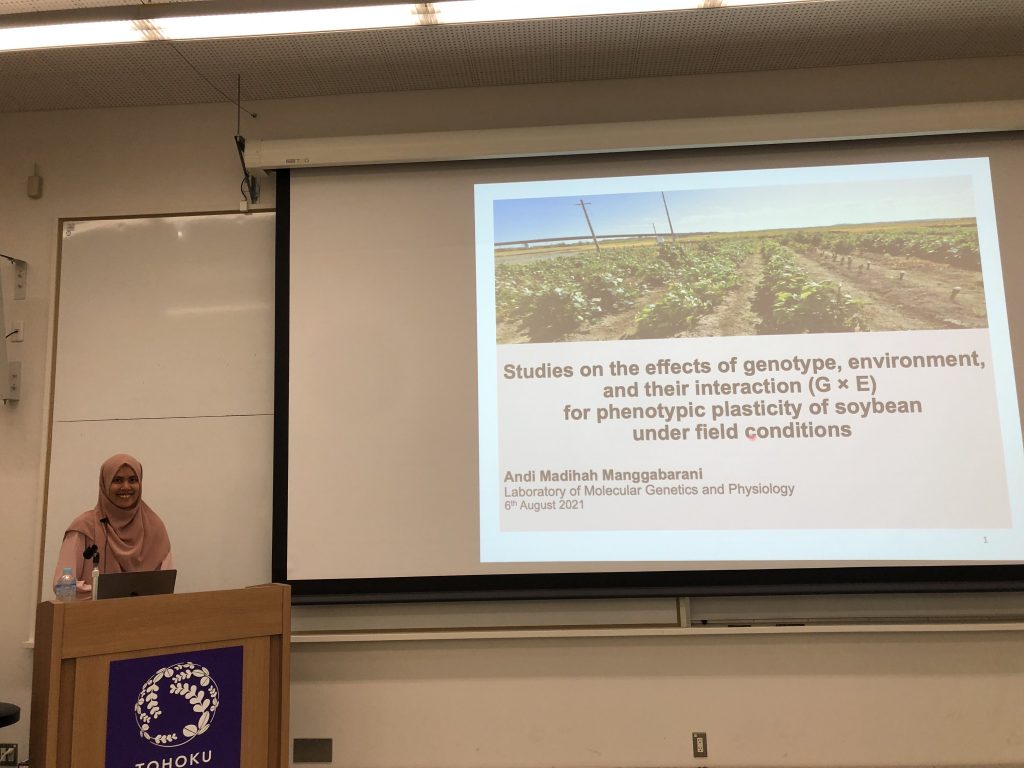当研究室の嵐田遥さん (D2) の論文がISME Journalに出版されました。マメ科植物に共生する根粒菌のゲノムは,生育に必須な領域 (コアゲノム) と共生関係の構築に必須な領域 (共生アイランド) から構成されています。根粒菌の共生アイランドには大規模な構造変化がよく観察されますが,その変異メカニズムは明らかになっていませんでした。本研究はダイズ根粒菌において,共生アイランド上に多数分布する挿入配列 (IS) の間で相同組換えが生じることで,ゲノムの欠失や重複がダイナミックに生じることを示し,またその構造変異が通常培養中に確率的に生じることを明らかにしました。このような共生アイランドの多様性創出機構は,宿主となる植物がより有用な共生者を選抜する一助となると考えられ,根粒菌を用いたマメ科作物の増収や減肥へつながるさらなる研究の発展が期待されます。
Haruka Arashida, Haruka Odake, Masayuki Sugawara, Ryota Noda, Kaori Kakizaki, Satoshi Ohkubo, Hisayuki Mitsui, Shusei Sato and Kiwamu Minamisawa. (2021) Evolution of rhizobial symbiosis islands through insertion sequence-mediated deletion and duplication. ISME J. [Link] [プレスリリース] [報道]